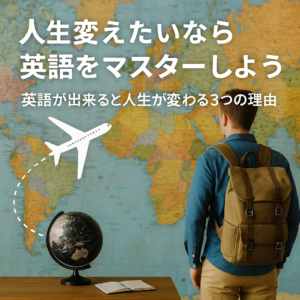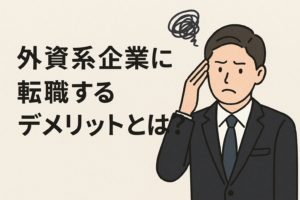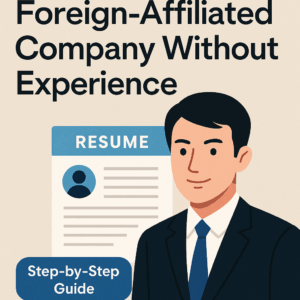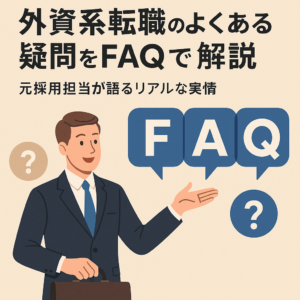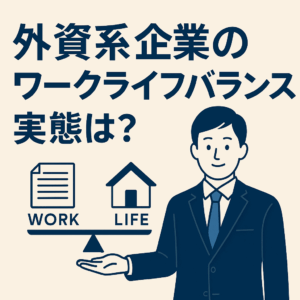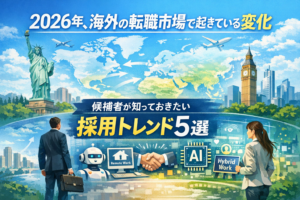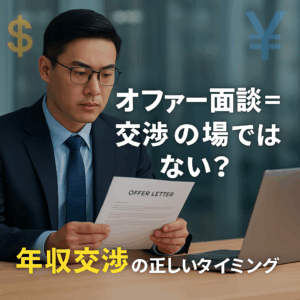「シンガポールは給料が高い」「日本はもう給料では勝てない」―こんな声を聞いたことはありませんか?
確かに、アジアのハブとして多国籍企業が集まるシンガポールは、給与水準が高く、国際的なキャリアを求める人にとって魅力的な存在です。
一方、日本はシンガポールに比べて国土が広く、地域によってライフスタイルや給与もバラバラです。
それに対して、シンガポールは国全体がまるごと一つの都会のような都市国家。
じゃあ「日本の都会=東京」として見たとき、東京での暮らしってシンガポールと比べてどうなの?と思ったのが、今回の記事の出発点です。
本記事では、シンガポールと東京を比較しながら、給料・物価・税金・社会保障・将来の安心といった「働く人が本当に知りたいポイント」を、最新データを元にわかりやすく解説します。
シンガポールで働いてみたいと考えている方も多いと思うので、ぜひ参考にしてみてください。
平均年収:東京とシンガポール、実際どっちが高い?
東京:
民間給与実態統計調査(2023年)によると、東京都の平均年収は約615万円。業種によって差はあるものの、外資系やITなどでは700〜1000万円超も珍しくありません。
シンガポール:
シンガポール人材庁(MOM)の統計では、2024年の大卒者の月収中央値は約S$5,200(日本円で約56万円/年収約672万円相当)。 ただし、外資系企業やテック企業に勤めるプロフェッショナル層ではS$8,000〜S$15,000(月収86〜160万円)も現実的。
【ポイント】 外資系でのハイクラス人材の平均を取ると、シンガポールの方がやや上。ただし業種・役職・年齢で逆転もあり、個人差が大きい。
海外では転職活動もAI活用が前提に。セルフブランディングの潮流も含めて、今どきの求職者トレンドをまとめました。こちらも↓ぜひ参考にどうぞ。

生活コスト比較:東京とシンガポール、物価はどちらが高い?
シンガポール:
- 家賃が非常に高い(都心1LDKで月25万〜35万円)
- 車は購入+維持で超高額(車両登録証制度:COE)
- 食品や外食も高め(特に輸入品)
東京:
- 家賃は23区内でも単身なら10〜15万円で選択肢あり
- 公共交通機関が発達しており車不要
- 外食の価格帯に幅があり、安く済ませやすい
【ポイント】 給与の高さだけでなく、「出ていくお金」も考慮すべき。シンガポールは高収入でも生活コストが高く、手元に残るお金は人によっては東京と大差ない可能性も。
- シンガポールの生活費は東京より約87%高い(Livingcost.org調べ)
- 他のデータでも 57〜75%高いとされ、負担は大きめ
- 手取りから生活コストを引いた余裕度
- シンガポール:約1.4か月分の余裕
- 東京:約1.5か月分の余裕
つまり、給与差を生活コストが打ち消し、実質の豊かさはそこまで変わらないという現実があります。
税金・社会保障の違いとインパクト
東京(日本):
- 所得税+住民税+社会保険料(厚生年金・健康保険など)で約25〜40%の負担
- 医療費は3割負担で済むなど保障が厚い
シンガポール:
- 所得税は累進課税だが、日本より圧倒的に低い(年収1000万円で約5〜7%)
- 社会保障費としてCPF(Central Provident Fund)への積立あり(給与の20%前後)
- 医療は自己負担が基本。メディセーブ(医療貯蓄)を使う仕組み
【ポイント】 シンガポールは税率が低く、手取りは多くなりやすいが、そのぶん公的な保障制度が少なく「自己責任」の側面が強い。
キャリア観の違い:シンガポール人は「今の収入」だけでなく「将来」も見ている
シンガポールでは転職が当たり前で、労働市場も流動的。 さらに、キャリアアップや収入増加の意識が非常に高く、「今の会社で将来がない」と判断するとすぐに転職を検討します。
また、政府がキャリアリスキリング支援や年金積立(CPF)を通じて「自己責任型」の将来設計を促しているため、若いうちから将来の備えを意識する人が多いのも特徴です。
PTOや柔軟な働き方など、海外のHR制度はどこまで進んでいるのか?働き方の価値観が気になる方はこちらも↓どうぞ。
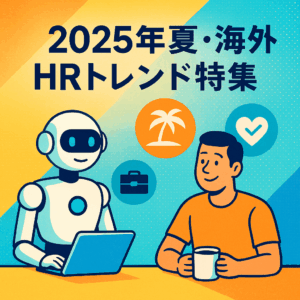
制度への信頼と前向きな将来設計
シンガポールは福祉国家ではないものの、「政府の支援制度の透明性」や「老後に備えるためのインフラ設計」が明確です。 たとえば、CPF(中央積立基金)では、雇用主と本人が拠出する形で、医療・住宅・老後資金を確保します。 また、公営住宅(HDB)の整備や、政府主導の研修制度など、個人の努力を後押しする仕組みが整っています。
一方、日本では制度が複雑で先が見通しづらく、「国に頼って大丈夫か?」という不安が世代を問わず広がっています。
年金制度比較:CPF vs 厚生年金
日本(厚生年金)
- 現役世代の保険料で高齢者を支える「賦課方式」
- 少子高齢化により将来の受給額への不安が高まっている
- 原則65歳から支給、加入年数と給与額で受給額が決まる
シンガポール(CPF)
- 完全積立型。現役時代の拠出分+利息がそのまま将来の生活資金に
- 65歳以降、CPF Life(年金制度)から終身年金が支給される
- 投資や住宅資金にも使えるが、老後資金が不足しないよう設計されている
【ポイント】 日本と異なり「自分で拠出して自分で備える」という仕組みのため、計画的に積み立てている人には安心材料が多い。
まとめ:シンガポールと東京、どちらが魅力的?
東京とシンガポール、どちらが働きやすいかは人によって異なりますが、
- 高い収入と引き換えに高コスト・自己責任で自由なキャリアがシンガポール
- 税負担は重くても制度が整っており安心感のある東京
という違いは明確です。
海外で働くことや暮らすことに興味があるなら、単に「年収がいくら高いか」だけじゃなくて、「実際の生活水準」や「将来への備え」も含めて考えるのが大事です。
日本にいても、こういう価値観や制度の違いを知っておくと、キャリアだけじゃなく、これからの人生をどう生きていきたいかを考えるヒントになるかもしれません。
【あとがき】シンガポールと東京、どちらも大好きな街
僕自身、シンガポールにはこれまでプライベートと仕事を合わせて10回ほど訪れたことがあります。
シンガポール人の友人はもちろん、現地で働いている日本人や、多国籍の友人もいて、個人的にも大好きな国のひとつです。
実は、以前シンガポールで本気で転職しようと考えたこともあります。
残念ながらその時はタイミングや条件が合わず断念しましたが、今でも訪れるたびに心が踊る場所です。
シンガポールの好きなポイントはたくさんあります。
街が綺麗に整備されていて、熱帯植物が街の中に生い茂っている景観、アジア太平洋のハブとして多国籍な人々が集まり働いている雰囲気、そして広々とした豪華なコンドミニアム。
どれも日本とは違った魅力を感じさせてくれます。
ただ一つ、酒好きとしては…外で飲み歩くとすぐにお金がなくなるほど酒代が高いのが悩みどころですね(笑)。
一方、東京は僕が生まれ育った街。
アンダーグラウンドからメジャーまで、音楽、演劇、ファッションなどの多様なカルチャーに触れられる自由な空気があり、そこが一番の魅力です。
気軽に色んな飲み屋を巡れるのも、個人的にはかなりポイント高いところ。
それに、日本国内のどこにでもすぐに旅行できるというのは、東京の強みでもあると感じています。
東京もシンガポールも、どちらも本当に魅力的な都市。
だからこそ、どちらかを選ぶのではなく、自由に行き来しながら働けるライフスタイルが実現できれば理想ですね。
あわせて読みたい関連記事