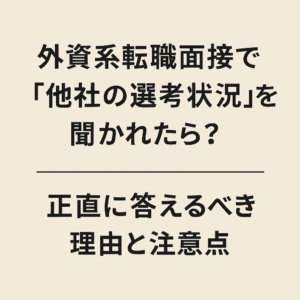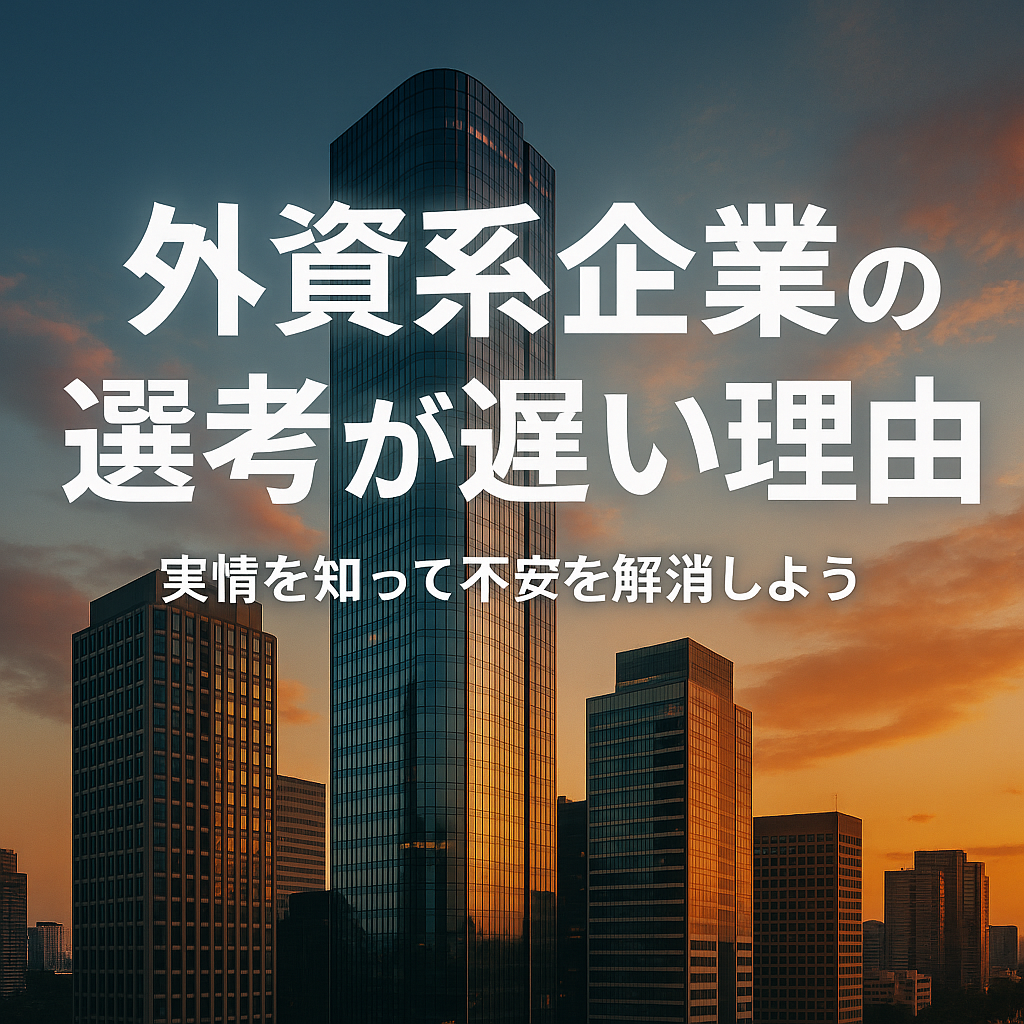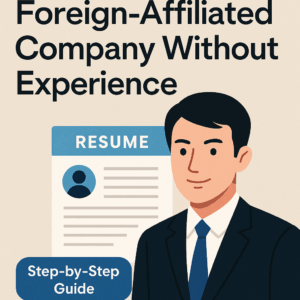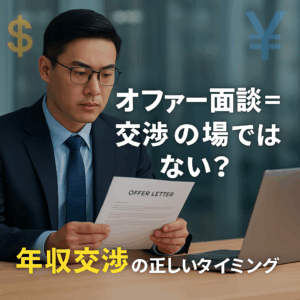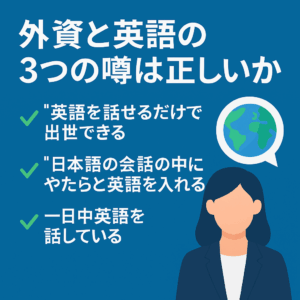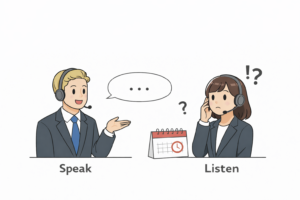外資系企業の選考は「結果連絡が遅い」「面接後に音沙汰がない」と悩む人が非常に多いです。
実際、私が採用担当として勤務していた時にも「なぜ連絡が遅いのか?」と質問を受けることが多くありました。
この記事では、外資系企業の選考が遅れる具体的な理由や採用側の事情を、元採用担当・エージェント・ヘッドハンターとしての経験をもとに詳しく解説します。
「なぜ待たされるのか」を知ることで、不安を減らし冷静に対応できるようになるはずです。
本社承認やグローバル承認に時間がかかる
採用決定権は基本的に日本国内のHiring Manager(部門責任者)が持っています。
しかし、そのHiring Managerの上司や、本社側が関与するポジションの場合は別です。
たとえば:
- 条件面(給与水準など)にグローバル基準が適用される場合
- ポジション自体がグローバル承認対象の場合
- 採用予算やヘッドカウント管理を本社が行っている場合
このようなケースでは、Hiring Manager自身も「採用したい」と思っているのに、本社側やグローバル人事の承認が下りないために決定できない状態になります。
また、承認を求める相手が海外本社の役員やシニアマネジメント層の場合、調整や意思決定に時間がかかるのが普通です。
日本側では選考を進めたいのに、グローバル側の承認待ちで動けなくなることは、外資系企業では日常的に起きています。
海外本社・関係者が長期休暇に入っている
外資系企業では、採用に関わる重要な決裁者が欧米の本社にいることが多いです。そのため、夏季休暇(サマーバケーション)やクリスマス〜年始にかけたホリデーシーズンなど、長期休暇に入ってしまうと採用判断自体が完全に止まってしまいます。
この間、日本側の採用担当者が何度連絡しても返事が返ってこないこともよくあり、現場は分かっていても応募者に進捗を伝えられない状況になります。
海外は祝日や長期休暇の取り方が日本と違います。
詳しくはお盆や年末年始に考える、日本の長期休暇と海外ビジネスマンのホリデー事情を参考にしてください。
出張や業務多忙で単純にレスが遅い
採用担当者やHiring Manager自身が出張に出ていたり、他業務で多忙な場合、単純に返信や次の判断が後回しになっていることも少なくありません。
特に採用活動を兼務しているHiring Manegerの場合、採用判断が業務の優先順位として後回しになることもあります。応募者側は不安に感じますが、現場では「今すぐ返信できないだけ」というケースも多いのです。
採用担当者と現場の意思決定が分かれている
外資系企業では、採用部門(HR)と実際の採用判断を行う現場部門が明確に分かれていることが一般的です。
採用部門は書類選考や面接調整までは迅速に行ってくれますが、最終的な合否判断は現場側(Hiring Manager)に委ねられています。そのため、現場の判断が遅れると、採用部門も応募者に何も伝えられない状況になります。
採用側は「現場から指示がないから動けない」というケースが実際には非常に多いです。
選考プロセス自体が形式的に長い
外資系企業の多くは、選考プロセス自体が多段階に設定されていることがあります。
- 面接回数が多い
- 最終面接後にも役員承認や本社承認が必要
- リファレンスチェックが必須
- 内定後のオファーレター発行までに内部承認が必要
こうした理由から、一見「最終面接まで終わったのに結果が来ない」という状況が発生します。

採用しない場合でも結果連絡しない企業もある
いわゆる「サイレント不採用」です。
日本企業であれば不採用の場合でも結果連絡をもらえることが一般的ですが、外資系企業では「不採用連絡をする」という文化自体がない会社も多くあります。
人事や採用担当者から連絡が途絶えた場合、それは「採用見送り」という判断が下されたサインであることも少なくありません。
特に書類選考の段階では、「連絡がない=不採用」と受け取ってほしい、という感覚の企業も少なくありません。
ポジション内容の変更や内部異動で採用方針が変わることも
選考中にポジション内容が変更されることもあります。
例えば:
- 想定より下位レベルでの採用に切り替わった
- 逆に上位職で採用することになった
- 組織変更や予算都合でポジション自体が見直された
さらに、採用を進めている最中に内部異動(internal transfer)で社内候補者が見つかり、外部採用が不要になることもあります。
こうした場合、外部選考が一時停止または打ち切りになり、応募者には理由が伝えられないまま結果連絡が保留されることもあります。
ヘッドカウント承認が採用途中で滞ることも
基本的には採用開始前にヘッドカウント承認は取得しているはずですが、
「確保できるはずだから先に動こう」という現場判断で採用が先行してしまうこともあります。
その場合、本社側でヘッドカウント承認が下りず、採用が停止してしまうこともあります。
現場と本社との調整に時間がかかっている間、応募者側は結果待ちとなることになります。
ヘッドカウント(採用枠)については、下記の記事も参考にしてください。
→ヘッドカウント=採用枠?外資系転職で知るべき人員管理と選考スピードの関係
外資系企業の採用における裏事情とは?
外資系企業の採用がスムーズに進まない背景には、日本法人と本社(グローバル組織)の間にある力関係や優先度の違いが大きく影響しています。
日本側の現場(Hiring Manager)が「早く採用したい」と思っていても、その要望が本社で必ずしも優先されるわけではありません。
本社側は日本法人の状況や市場を深く理解していないことも多く、「本当にその採用は今必要か?」と予算や組織の観点から再検討を求めるケースもあります。
特に以下のような場面で遅延が起こりやすいです:
- 本社側で「日本法人の採用は急ぎではない」と判断される
- グローバル視点で見た場合、日本での人員補充が優先度の低い課題になる
- 採用予算そのものが本社の管理下にあり、現場の要望よりも財務的な制約が優先される
- 採用ポジション自体が本社戦略次第で見直されることがある
つまり、日本側の「早く採りたい」「人が足りない」という状況は、本社側の判断基準では必ずしも重要とは見なされないのです。
日本法人は「お願いしている立場」になることが多く、採用は本社側のリソースや戦略次第で進むか止まるかが左右されます。
このため、現場や日本法人が焦っていても採用判断が進まず、選考が長引いたり、採用がキャンセルされることもあります。
こうしたグローバル企業特有の意思決定構造が、外資系企業の選考が遅くなりやすい背景の一つと言えるでしょう。
連絡が遅いときの対処法・心構え
- 面接後、2週間程度は待って問題なし
- 2週間前後待って連絡がなければ、状況確認の連絡を
- 返事がないなら見切りをつけて次へ進むことも重要
- 外資系企業では「待たせることに罪悪感がない」ことも多いため、応募者側が深刻に考えすぎないことが大切
また、外資系企業では採用がフリーズしたり、調整が進まないまま選考がお流れになることも珍しくありません。
そのため「絶対に転職したい」という場合は、1社に絞らず複数社の選考を並行して進めることでリスクを減らすことも大切な戦略です。
転職活動の進め方に迷っている人は、LinkedInと転職エージェントのおすすめの使い分けを比較解説をご覧ください。
まとめ
外資系企業の選考は遅くなることが普通です。
本社承認や休暇、内部調整などの事情によって、採用側で選考が止まっていることも少なくありません。
こうした裏事情を知っていれば、無駄に焦ったり不安になりすぎる必要はありません。
とはいえ、選考が実際にフリーズしてしまうケースもあります。
そのため、1社に絞らず複数社の選考を並行して進めることで、リスクを減らしながら転職活動を進めていくことをおすすめします。
外資系企業の選考スピードに関するFAQ|よくある質問と回答
Q1. 外資系企業の選考はどのくらい時間がかかるのが普通ですか?
A. 職種やポジションによりますが、書類選考から内定まで平均で1〜2か月かかるケースが多いです。特に海外本社の承認が必要な場合は、さらに長引くことも珍しくありません。
Q2. 連絡が遅いのは不採用のサインでしょうか?
A. 必ずしも不採用とは限りません。外資系では本社決裁者の休暇や出張で承認が滞ることも多く、採用プロセスが一時的に止まることがあります。数週間程度であれば通常の範囲と考えてよいでしょう。
Q3. 選考が長引いたとき、応募者ができる対応はありますか?
A. 2週間以上連絡がない場合は、エージェントや採用担当に進捗を確認するのがおすすめです。待つだけでなく、自分から丁寧に確認することで安心できますし、応募への熱意を伝えることにもつながります。
Q4. 日本企業と比べて、外資系はなぜ選考が遅くなりやすいのですか?
A. 外資系ではグローバル承認やヘッドカウント承認が必要になるためです。また、日本支社だけで決められず、本社の複数部署を経由して判断されることが多く、時間がかかる傾向にあります。
Q5. 選考が遅い企業を見分けるポイントはありますか?
A. 面接時に採用プロセスの全体像や内定までの期間を確認しておくと安心です。また、過去の口コミやエージェントの情報から選考スピードを事前に知ることもできます。詳しくは「 外資系企業の面接プロセスの注意点」も参考にしてください。
この記事を読んだ方はこちらの記事もどうぞ